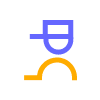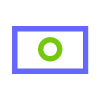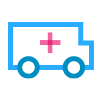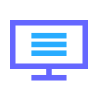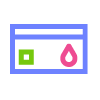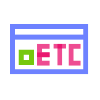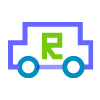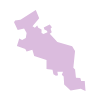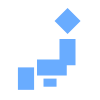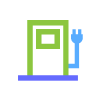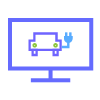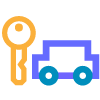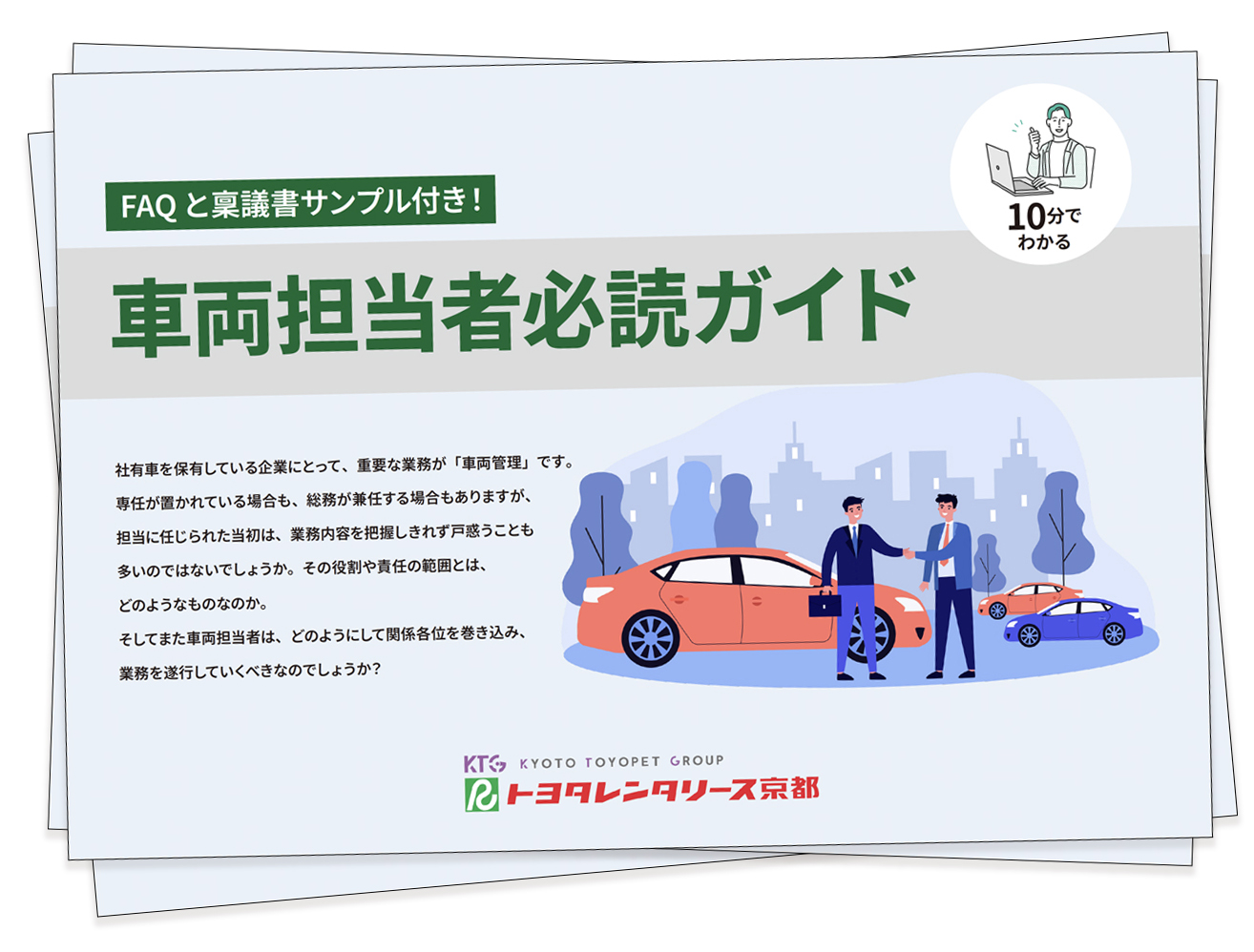社用車を運用していく上で、車両管理責任者と安全運転管理責任者が押さえておくべき点検は「車検」「定期点検」「日常点検」の3種類です。このうち「車検」「定期点検」はプロの領分ですが、「日常点検」は、自社内で責任をもって実施しなければなりません。今回のコラムでは、この「日常点検」に着目し、その内容や頻度について解説していきます。

「車検」「定期点検」「日常点検」の違い
これらはいずれも、いわばクルマの健康チェックですが、それぞれの実施頻度や意味合いが異なり、相互に補い合う関係になっています。車検(自動車検査登録制度)は、クルマが保安基準に適合しているかを検査する制度。安全性や公害防止面などで問題がないかをチェックします。※新車の場合は購入3年後、それ以外は2年ごとの頻度で受けることが求められます。(※自家用乗車の場合)
定期点検は自動車の故障を未然に防ぎ、性能維持を図るための予防点検です。12ヶ月点検や24ヶ月点検があるほか、バス、トラック、タクシーなどの事業用車両は3ヶ月ごとなど、対象自動車によって、点検の頻度と点検項目数が異なります。
さて、では日常点検について、以下に見ていきましょう。

日常点検はなぜ行うのか
車検や定期点検だけでは、上記のような頻度の問題もあり、クルマの日々の健康状態はチェックしきれません。そのため車両管理責任者や安全運転管理責任者が音頭を取って、社用車を実際に運転するドライバーと協力し、「日常点検」を行わなければなりません。これは故障やトラブルを早期に発見し、整備不良で走ったりするようなことのないようにするために必要なことです。
道路運送車両法第四十七条には、〈使用者の点検及び整備の義務〉として、以下のように定められています。
「自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない」。
また、第四十七条の二には、〈日常点検整備〉として、以下の規定があります。
「自動車の使用者は、自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に、国土交通省令で定める技術上の基準により、灯火装置の点灯、制動装置の作動その他の日常的に点検すべき事項について、目視等により自動車を点検しなければならない」。
ここで述べられている「国土交通省令で定める技術上の基準」については、国土交通省のWebサイトで確認することができます。ここでは、サイト上に掲載されている「日常点検項目チェックシート」に沿って、具体的な日常点検の項目をチェックしていきましょう。
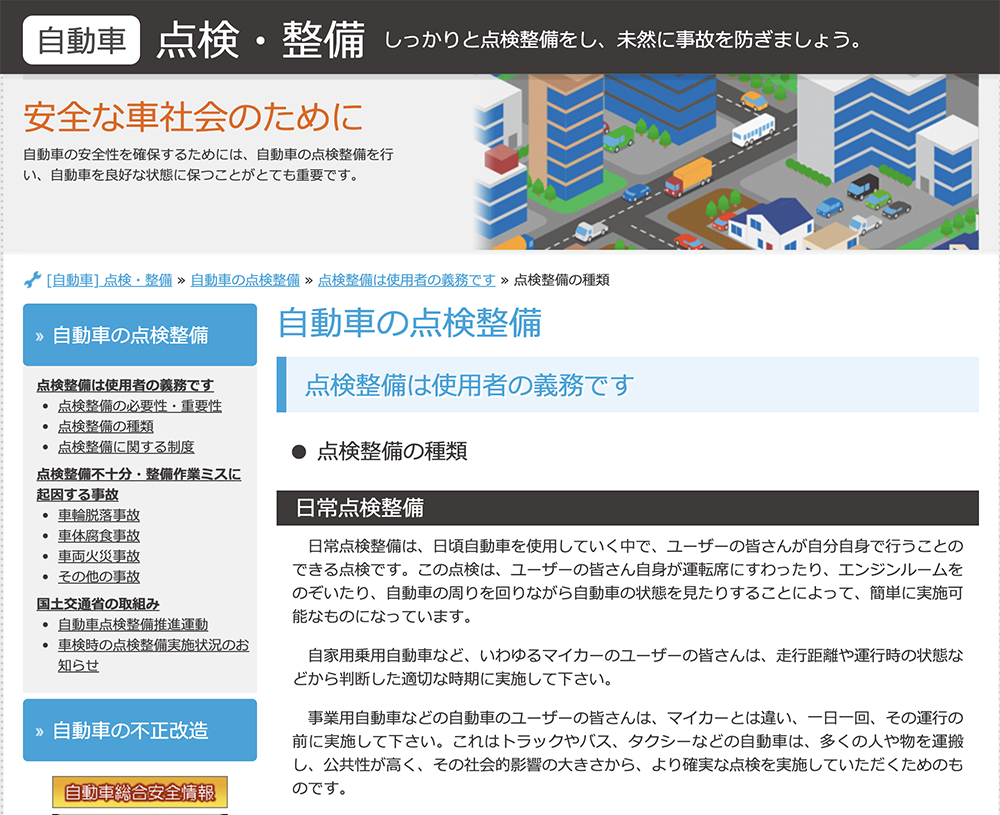
「日常点検項目チェックシート」に記載されている15のチェック項目
エンジンルーム:5項目
1 ブレーキ液の量
2 冷却水の量
3 エンジン・オイルの量
4 バッテリ液の量
5 ウインド・ウォッシャ液の量
クルマの周り:4項目
6 ランプ類の点灯・点滅
7 タイヤの亀裂や損傷の有無
8 タイヤの空気圧
9 タイヤの溝の深さ
運転席:6項目
10 エンジンのかかり具合・異音
11 ウインド・ウォッシャ液の噴射状態
12 ワイパーの拭き取り能力
13 ブレーキの踏み残りしろと効き具合
14 駐車ブレーキの引きしろ(踏みしろ)
15 エンジンの低速・加速状態
いかがでしょうか。どのようにチェックするかの詳細はシートに記載がありますが、「15の項目は多いな」と感じられたかもしれません。しかし逆にいえば、これだけの機能チェックをしなければ、クルマのトラブルを予防し、安全・安心に運転することは難しいのだ、といえるかもしれません。
チェックのコツとしては、このチェックシートの通りに「エンジンルームを覗き」「クルマの周りをぐるっと巡って」「運転席内でチェックを完了させる」という動線をつくり、それに沿ってチェックすることをパターン化して、クセ付けてしまうとよいかもしれません。
日常点検を行う頻度はどれくらい?
さて、この日常点検ですが、いったいどれくらいの頻度で行うべきなのでしょうか。先ほど引用した道路運送車両法第四十七条の二では「自動車の走行距離、運行時の状態等から判断した適切な時期に」という記載になっており、具体的な頻度は記載されていません。トラックやバス等の事業用自動車では、1日1回実施すべきことが明確に定められていますが、社用車の多くは自家用自動車のカテゴリーに属します。
そうすると、具体的にはどれくらいの頻度で実施すべきなのでしょうか?ランプの球切れやタイヤの亀裂などは常に発生する可能性もありますので、運行前には必ずチェックした方が良いでしょう。
そして少しでもクルマに異変を感じるようなことがあれば、代替車両に切り替えるなどの措置を取り、不調の原因については、整備工場のプロの手に任せるようにしましょう。

日常点検を行わなかった場合に罰則はある?
上に見てきたように日常点検は法律で義務付けられていますが、罰則規定はありません。ですから実施頻度や内容については、企業に一任されている状態となっています。しかし罰則規定が明示されていなくとも、日常点検の不備による事故が発生した場合には、企業や車両管理者が道義的責任を問われる可能性もあります。
なにより、日常点検を行わないことは、整備不良を放置することを意味し、自社の大切な社員を危険に晒し、重大な交通事故を招くことにもなりかねません。リスクマネジメントの観点からも、日常点検を欠かさず行うことは必須といえるのではないでしょうか。
いかがでしたでしょうか。
トヨタレンタリース京都では、京都府下の法人様、または個人営業主の皆様に役立つサービスの提供と、情報の発信に努めています。
私たちの信条は、カーリースにとどまらず、お客様ごとのお困りごとに寄り添って対応する、ソリューションのご提供です。
クルマに関するお困りごとやご相談は、トヨタレンタリース京都に、どうぞお気軽にお寄せください。