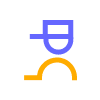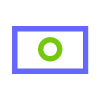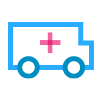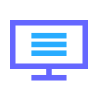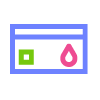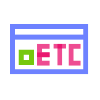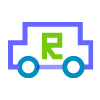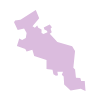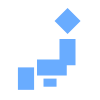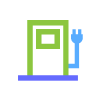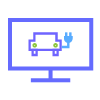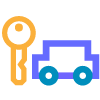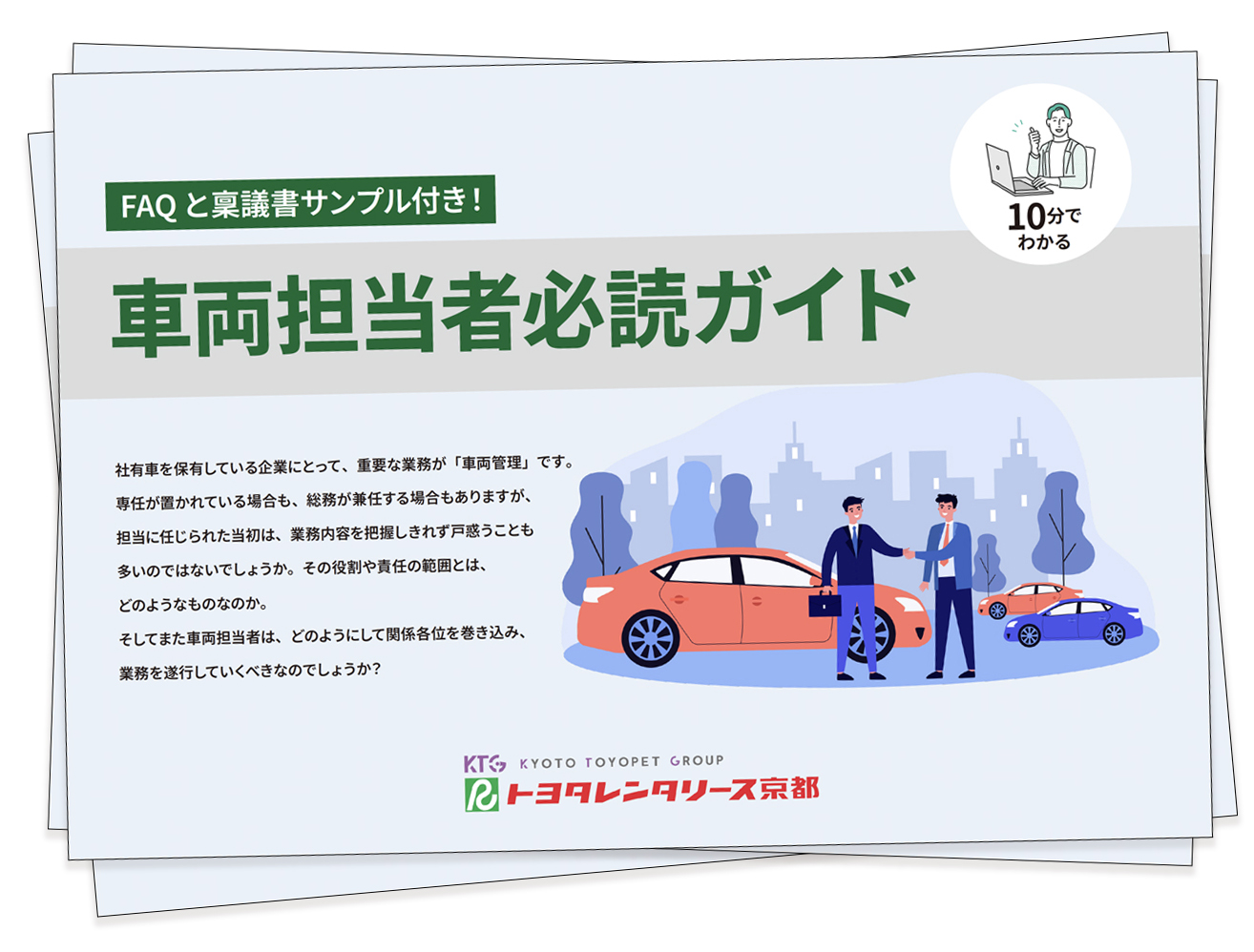クルマ関連の話題で「ハッチバック」という言葉を読んだり、耳にしたりしたことがあるでしょうか。多くのクルマ用語同様、この言葉も説明なしに使われることが多いため、正確に知らなくても、つい読み飛ばしてしまったりということもあるのではないでしょうか。本コラムでは、ハッチバックの意味や歴史について丁寧に説明します。また、数あるトヨタ車の中からオススメのハッチバックもご紹介しますので、ぜひ最後までお付き合いください。

トヨタ ヤリス
ハッチバックとは、どんな車種?

トヨタ カローラスポーツ
ハッチバックとは、車体の後部が跳ね上げ式あるいは横開き式のドア(バックドア)になっていて、車室と荷室がつながっており、独立したトランクルームのないクルマのことです。一般的には、この条件を持った、小型で取り回しやすい、いわゆる「コンパクトカー」のことをハッチバックと呼んでいます(より狭い意味では、「全長が4600mm以下、車高が1550mm以下」といった条件が付くこともありますが、このあたりはかなり曖昧で、メーカーの呼称次第で変わります)。
バックドアは、その名称の通りドア扱いになるので、車体左右のドアが2ドアの場合はバックドアを加えて「3ドア」と呼ばれ、4ドアの場合は「5ドア」と呼ばれます。
これに対して、セダンやクーペといった独立したトランクルームを持った車種ですが、トランクの開閉部はドア扱いにならないため、例えば車体左右のドアが4ドアなら4ドアセダン、2ドアなら2ドアクーペ等といった呼称になります。これらのクルマには、車室と荷室を隔てる仕切り壁(バルクヘッド)が存在しますが、ハッチバックにはこのバルクヘッドがないのが、構造上の大きな違いです。
ハッチバックの言葉の由来とは?
クルマにおいて、人が乗り込むドアの開閉の形式は、スイングドア(上から見て扇形に開く)や、スライドドアといったかたちを取ります。それに対してハッチバックの後部(バック)にあるドアは上に跳ね上げることから、これを船などのハッチに見立てて「ハッチバック」と呼ばれるようになったと言われています。

ハッチバックの歴史
ハッチバックの元祖は、1961年の「ルノー4(この4は、フランス語なので「キャトル」と読みます)」であると言われています。その後の1974年、イタリアを代表する著名な工業デザイナーであるジョルジェット・ジウジアーロがデザインした「フォルクスワーゲン・ゴルフ」の初代モデルの世界的成功によって、ハッチバックは広まっていくことになりました。ここ日本では、フォルクスワーゲン・ゴルフに遡る1966年の時点で「トヨタ・コロナ5ドア」が発売されています。
ハッチバックは、当初は商用バンかと勘違いされるほどに認知が低かったようですが、次第にコンパクトな車体と優れたユーティリティの魅力を打ち出した数々のモデルの登場によって人気を獲得し、現在では、小型自動車や軽自動車の主流を占める車種となっています。
ハッチバックのメリット
ハッチバックのメリットの1つに燃費が上げられます。車体がコンパクトなため車重が軽く、空気抵抗も少ないので燃費性能が高いのです。この観点からは、特にハイブリッド車がオススメといえるでしょう。
またコンパクトで取り回しが良いことから、運転のしやすさも魅力です。セダンのようにトランクルームが後部に突出している形状ではないので、車両感覚がつかみやすいでしょう。例えば京都の狭い道を走るといったシチュエーションでも、ハッチバックなら無理なくクルマを通らせることができます。
また、ハッチバックは人が乗るスペースと荷室が一体のため、車を降りずとも、移動中であっても荷室から荷物を取り出すことができます。これはファミリーユース、あるいは旅行中といったシチュエーションなどでも役立つでしょうし、もちろん、社用車としての利用の際のメリットともなるでしょう。

トヨタ ライズ
そしてハッチバックは、後部座席を倒せば大容量の荷物や長尺の荷物を積み込むこともできます。そのため、普段使いにはコンパクトな乗用車サイズで十分だけれども、たまに大きな荷物を運ぶことがある、といったニーズにはぴったりの車種選択になるでしょう。

トヨタ ライズ

トヨタ カローラフィールダー
ハッチバックのデメリット
これはハッチバックのメリットと表裏一体ですが、荷室と人が乗るスペースが一体のため、後部座席を倒して大きな荷物を積み込むといった場面では、その分、乗ることのできる人数が限られます。逆に乗員が増えると、荷物の積載スペースが減ります。
もう一点、静粛性の問題があります。ハッチバックは、乗車スペースとトランクルームを仕切るバルクヘッドがないという構造上、リヤタイヤからのロードノイズが車内に入ってきやすいのです。そのためセダンと比較すると、車内がややうるさく感じられるかもしれません。しかし最近のモデルでは、静粛性を高める様々な工夫がされていますので、大分解消されてきている部分といえるかと思います。
それからハッチバックのまさに「ハッチ」の部分に関することですが、跳ね上げ式にせよ横開き式にせよ、車体後部にスペースがないとドアの開け閉めや荷物の積み下ろしができませんので、駐車時にはその点を考慮することが必要です。
トヨタのハッチバック「プリウス」
社用車としてのオススメポイントもご紹介!
さて、ここからはトヨタのハッチバックの中でもオススメの車種をご紹介していきます。トップバッターは、現在5代目が発売されている「プリウス」。世界初の量産ハイブリッド専用車(スプリット方式)として、1997年に市場に登場しました。「燃費の良さ」「ちょうど良いサイズ感」「運転のしやすさ」といったメリットを備え、日本のみならず世界的にも人気の車種となっています。


このプリウスが、セダンからハッチバックへと大きな転換をしたのが、2代目へのフルモデルチェンジのタイミング。時に2003年のことでした。セダンは現在ではどちらかというと保守的・伝統的というイメージを与えますから、そこから脱却して、2代目にして若々しく新鮮なイメージを打ち出したわけです。プリウスという名前の由来は「〜に先駆けて」という意味のラテン語ですが、名前の通りの先見の明があったわけです。
運転しやすく、維持費が低く、幅広い層に「エコ=プリウス」というイメージの浸透しているこのクルマは、社用車としてもまさに「ちょうど良い」選択といえるでしょう。

トヨタのハッチバック「アクア」
社用車としてのオススメポイントもご紹介!
2011年12月に誕生したトヨタ「アクア」。5ドア、ハッチバック型のボディにハイブリッドシステムを組み合わせたコンパクトカーというコンセプトは市場に好評を持って迎えられ、日本のみならず世界的なベストセラーとなりました(世界市場における名称は「プリウスC」。Cは「City」のCですが、いわば、プリウスのコンパクトカーとして位置付けられていたことが推察されますね)。

アクアといえば、なんといっても、世界トップレベルの低燃費。2014年に国土交通省が発表した「燃費の良い乗用車ベスト10」では、普通・小型車部門で1位となっています。
また、「快感ペダル」の採用も特徴。踏み込めばまるでEVのようにスムーズに加速が伸び、アクセルオフでは減速度が強くなることによって、アクセルペダルのみでの速度調節が可能。アクセルとブレーキの踏み替え頻度を減らして、ドライバーの疲労を軽減します。
コンパクトで小回りの効く車体、そして燃費の良さは、「営業の足」としても、日々、大活躍してくれるでしょう。法人ユースとしても大いにオススメです。

トヨタのハッチバック「ルーミー」
社用車としてのオススメポイントもご紹介!
「ルーミー」のコンセプトは、広々とした空間「Living」と余裕の走り「Driving」をかけ合わせた「1LD-CAR(ワン・エル・ディー・カー)」。 まさにキャッチコピーが示すように、「使える!動ける広い部屋!」といえます。車両寸法は、3,700 mm(X、G)ないしは3,725 mm(カスタムG、カスタムGーT)×1,670 mm×1,735 mm。この5ナンバーのコンパクトなボディの中に、ゆったりくつろげる室内空間が広がっているのが大きな魅力です。

そして、ハッチバックの可能性を最大限に引き出してくれる、多彩なシートアレンジ。リヤシートは6:4可倒式になっていて、別々にスライド可能。前方にダイブイン格納させると、自転車などの大荷物や、カーペットなどの長尺ものも積載できます。
例えば社用車を選ぶ際、「営業の足になれば良いのでアクアやヤリスで十分」といった場合にも、もし荷物を積むシチュエーションが発生しそうなら、敢えてあらかじめルーミーというのが、ベストの選択肢になるかもしれません。

いかがでしたでしょうか。
トヨタレンタリース京都では、京都府下の法人様、または個人営業主の皆様に役立つサービスの提供と、情報の発信に努めています。私たちの信条は、カーリースにとどまらず、お客様ごとのお困りごとに寄り添って対応する、ソリューションのご提供です。
クルマに関するお困りごとやご相談は、トヨタレンタリース京都に、どうぞお気軽にお寄せください。